最新の投稿
アーカイブ
2025年05月13日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

中小企業の経営者にとって、役員退職金は"会社人生の集大成"ともいえる重要な資金です。
これまで会社の成長に身を捧げてきた分、最後にはしっかりと報われたい。
そう考えるのは当然のことです。
しかし、近年の税務調査では、役員退職金が「過大支給」だとして
否認される事例が急増しています。
特に中小企業では、退職金に関する規定が曖昧であることや、
実質的な退職していないケースが多く、思わぬリスクを抱えていることも。
本ブログでは、税務否認という"落とし穴"に陥らないために、
経営者が知っておくべき3つの重要チェックポイントを解説します。
制度設計や運用の見直しを図るきっかけとして、ぜひ最後までご覧ください。
まず、最も多くの経営者が見落としがちなのが、支給金額の「妥当性」です。
いくら功労があるからといって、金額が高すぎれば、
税務署は"過大"と判断し、損金算入を否認します。
一般的な退職金の算定式
退職金額 = 最終月額報酬 × 役員在任年数 × 功績倍率
このうち「功績倍率」は、役職や業績に応じて変動するもので、税務署が特に注視する項目です。
社長の功績倍率の目安は「2.0倍〜3.0倍」とされているケースがほとんどです。
これを超える倍率を用いる場合、客観的な資料や同業他社との比較データが求められ、
何の説明もなく5倍・6倍といった数字を用いて高額な役員退職金を支給した場合、
否認リスクは非常に高くなります。
よくあるNG例:
税務否認を避けるには、業界の水準と整合性のある計算根拠を整えておくことが必要です。
次に重要なのが、社内における手続きの「整備」です。
中小企業の場合、「社長の判断で金額を決めて支払っている」ケースが
少なくありませんが、これは税務上非常に危険です。
求められる社内の整備項目
他の役員との整合性
社長のみが突出して高額になっていないか?バランスは取れているか?
最後に見落としがちなのが、「退職の実態」です。
中小企業では、社長が代表取締役を退いた後も、
"実質的な経営権"を保持しているケースが珍しくありません。
税務署が見る「実質的な退職の有無」
以下のような状況では、「退職とはみなされない」可能性があります。
つまり、役職上は退職していても、実態として業務に携わっていれば、
形式的な退職とみなされ、退職金は否認されるのです。
役員退職金は、経営者にとって老後資金の中核となる重要な財源です。
しかし、支給する金額が過大であったり、退職の事実が無かったりすると
否認リスクが高まり、思い描いたセカンドライフではなくなることも考えられます。
今回ご紹介した3つのチェックポイント:
この3点を専門家と事前に確認し、
確実に役員退職金を受け取る体制を整えることをおすすめします。
ヒューマンネットワークでは全国の中小企業経営者の
課題解決をお手伝いしている、生命保険代理店です。
27社の保険会社から各企業の状況とビジョンに合わせた、
最適なプランをオーダーメイドで作成しております。
将来の役員退職金についてご不明などございましたらお気軽にご相談下さい。
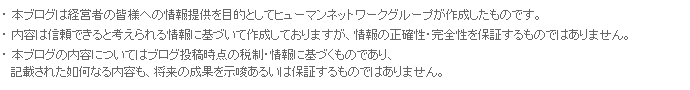
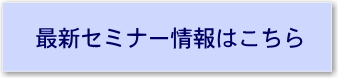 |
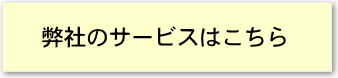 |
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。