最新の投稿
アーカイブ
2023年08月16日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

8月24日15:00までの期間限定公開です。
こんにちは。
ヒューマンネットワークグループの代表の齋藤です。
平素は大変お世話になっております。
さて、今回は私がやっている自社株対策についてお伝えします。
というのも度々ですが、お客様から
『ところで齋藤さんはどうしているの』
という質問をいただくことがあります。
そこで今回は、私の体験と対策についてまとめてみました。
私が皆さんにもっともお伝えしたいポイントを書かせていただきましたので、
お付き合いいただければ幸いです。
事業がそこそこ順調であることは、
すべてのオーナー社長の願いではないでしょうか。
しかし、順調であればあったで、
オーナー社長を悩ませるのが自社株の承継問題です。
以下のものを真剣に検討しました。
・ホールディングス(持ち株会社)
・自社株の評価下げ対策各種(オペレーティングリース等)
・贈与や譲渡
・不動産の購入
・事業承継税制
・従業員持ち株会
・投資育成 等々
みなさんの中にも、
このような対策を勧められている方が
いらっしゃるのではないでしょうか。
じつは、私も数年前に死にかけた時、
銀行や証券会社・コンサルを招いて、あらゆる自社株対策を検討したので、
このあたりのことは、わがこととしてよく知っています。
弊社には相続に関するご相談、
特に自社株対策についてのご相談を多くいただいていますが、
みなさんの関心は、
『いろいろある自社株対策の中で、何がいいのだろうか?』
ということだと思います。
そのようなときに、私が死にかけたこと、
そしてさまざまな自社株対策を検討した時の
体験談をお聞きいただいています。
とどのつまり、「それで結局、齋藤さんはどうしたの?」
と尋ねられますので、私は自信を持って
「金庫株の一択にしました。」と答えます。
実際、私はさんざん検討した結果、
(私の場合は)金庫株が一番適していると思ったのでそうしたわけですが、
「詳しく教えてください!」と言われる事が多いので、
今回、ポイントをまとめておきたいと思います。
金庫株を極めて簡単に言うと
社長が保有している株式を発行会社に買い取ってもらうことです。
思い切って単純に書くと、具体的には次のような流れになります。
1. 相続が発生し、家族が自社株を相続する
2. 相続税の負担がある
3. 相続した株式を会社が相続人から買い取る
4. 自社株を相続した人は、その資金で納税する
これで、頭の痛かった自社株の問題は解決です。
みなさんの疑問は、こうではないでしょうか。
「そもそも、会社が相続人の株を買い取ることができるのか?」
「それにメリットがあるのか?」
会社が株主から自社株を買い取ることはできますが、
税率が高いために一般的には実施されません。
(配当所得として 最高55%の税率になります)
それが、相続の時に限り税率は20%になるのが国の特例なんです。
さらに、個人が支払った相続税分は
「取得費」として控除できるので、
実効税率は、さらに低下します。
こんな特例を活かさない手はないと思いませんか?
ただし、会社に株を買い取るだけの財源がなければダメです。
それも、配当(分配)可能利益と言って税引後の利益と現金が必要です。
なかなかそれだけの現金をいつも手元に置いてある会社はないでしょうから、
資金の準備をしておかなければならないことが
金庫株のハードルになっていると思います。
もっとも、これは社長が生命保険に加入しておくことで難なく準備できます。
(生命保険の種類は吟味する必要があります)
これはつまり、相続税の財源を自己負担無し、
会社の経費で準備できることに他なりません。
しかも、生命保険ですから「今すぐに!」準備することが可能です。
(保険に入れない人は、方法はありますので個別にお問合せください)
金庫株の利点として
(1)自己負担なし(会社負担)で納税資金が準備できる
(2)いつでも後戻りができる(やめたくなったらいつでもやめられる)
(3)「経営権の集中」が可能になる
(4)配偶者の株も買い取ることで、配偶者の老後資金ができる
(5)当面のリスクから解放される
といったことが挙げられます。
金庫株で必要最低限の対策を行い、将来、
・自分に合った良い方法が見つかった場合
・現行の法制・税制では、できない承継対策が実行可能になった場合 には、
その時点で適した方法に乗り換えることができます。
つまり、事業承継に保険をかけるのと同じ意味を持ちます。
ここで、(2)の「後戻りできる」ということに説明を加えると、
冒頭で紹介した一般的な自社株対策で二の足を踏んだのは
「どの方法も後戻りが容易でない」
という問題があったからです。
持ち株会社などの方法は、
その時は良くても、一旦始めてしまうと状況が変わった時に
「簡単にはやめられません」。
何か不測の事態が起きて、
後戻りしたいと思ってもできないことが
とてつもなく大きなリスクに感じられたわけです。
というのも、私共がお客さまのご相談を受けている中で、
自社株対策でひどい目に合っている社長を何人も見てきたからです。
例を挙げますと
・業績が続かず相続税対策が必要なくなった
・事業が不振になり、銀行からの借金を返せなくなってしまった
・本業以外の事業(不動産事業など)が上手くいかず、辞めたくなった
・予定していた後継者が退職してしまい計画が狂ってしまった
・肝心の後継者が亡くなってしまい、株が嫁に渡ってしまった
などです。
自社株対策のほとんどは10年、15年という長いスパンで考えるものです。
そこで起きるのが「状況が変わってしまう」というリスクです。
結局、リスクを抱えてまですべきか、という疑問を抱いたわけです。
10年先まで曇りなく見渡せる事業など、まず存在しません。
長期の対策はそれ自体がリスクだというわけです。
一見良さそうな従業員持ち株会や、投資育成も、やめようとしたら大変です。
その点、生命保険による金庫株対策は
すぐ実行できて、やめたくなったらいつでもやめられます。
やめたことによる障害もありません。
それまでの保険料負担はありますが、
万一の時は保険金が出るわけですから、ムダな費用ではありません。
ただし、単に生命保険に入っておけばいいというものではありません。
社長が万一のときに備えて、
保険金の使い道についてはっきりと決めて、
指示書として残しておく必要があります。
決めたことがちゃんと実行できるように、
法的拘束力を持たせることが必要です。
ここが本日お伝えしたい最大のポイントです。
意外にも、会社と家族がもめることが多いからです。
例えば、
配偶者が会社経営に関与していない場合、
後継者が決まっていない場合
などは、トラブルになる可能性が高いです。
このトラブルを避けるためには、法的な対策が必要です。
言い方を変えれば『会社への遺言書』を準備するということです。
私は、この方法に気づいて実行してからは、
「当面のリスクから解放」され、
同時に、いろいろな業者との煩わしい面談や、
本業に集中できない葛藤なども霧散しました。
そして経営に専念できる状態になりました。
私自身が実行して、とても良いと感じておりますので、
自身をもってお伝え出来ます。
本ブログの執筆にあたっては、
細心の注意を払ったつもりではありますが、
至らぬ点もあろうかと思います。
お読みいただいた皆様のお気づきの点があれば、
ぜひ、ご指摘いただければ幸いです。
なお、金庫株を成功させるために必要な知識を
簡単にまとめた動画を作成致しました。
下記フォームよりお申込みいただくとすぐに
無料動画をご覧いただけます。
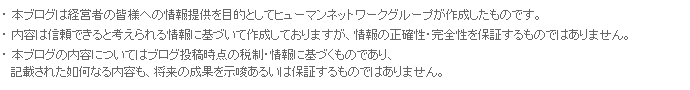
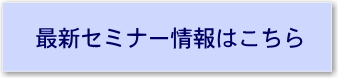 |
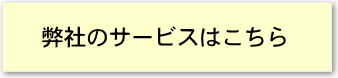 |
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。